-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
投稿日カレンダー
2026年2月 日 月 火 水 木 金 土 « 1月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
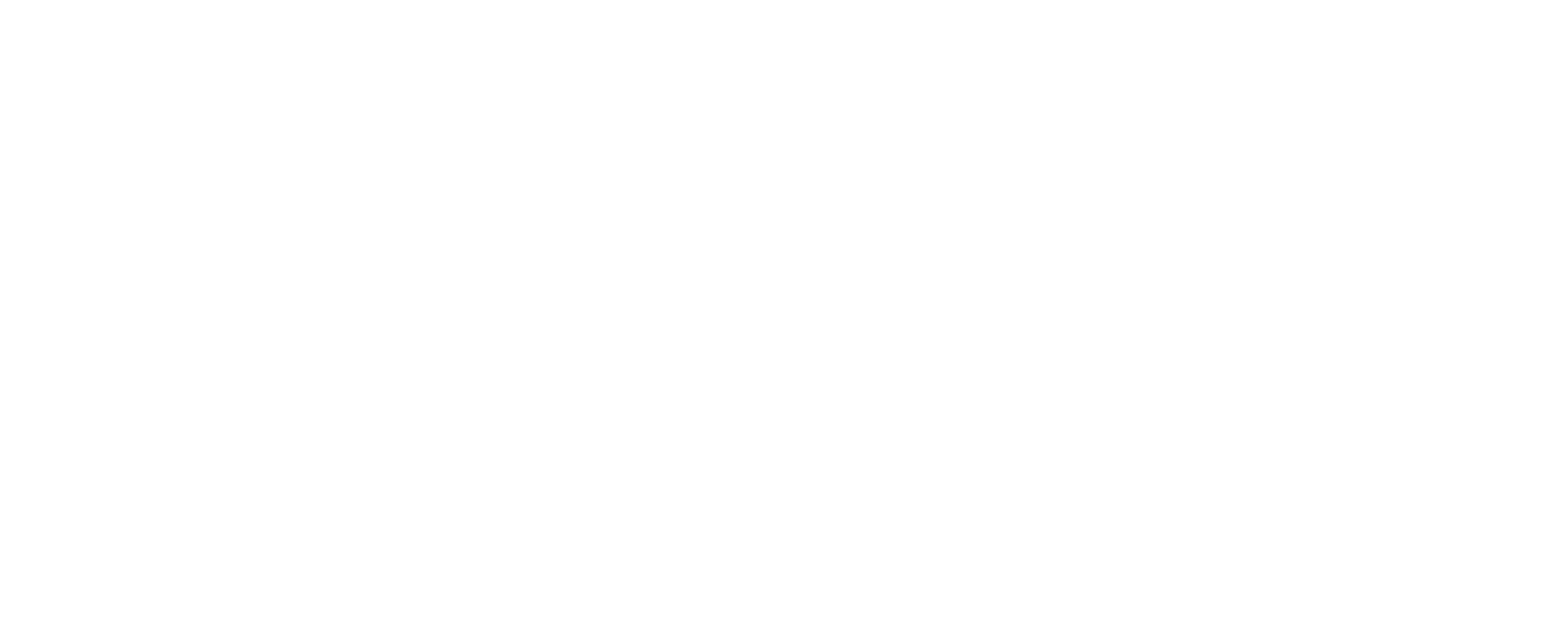
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
「バーとは?」
~大人のくつろぎ空間で特別なひとときを!~
皆さんは「バー」と聞いてどんなイメージを思い浮かべますか?「ちょっと敷居が高そう…」「おしゃれで大人な場所?」そんなイメージを持つ方もいるかもしれませんね。でも、実はバーはとっても気軽に楽しめる、特別な時間を過ごせる場所なんです!
今回は、そんな「バー」の魅力や楽しみ方についてお話しします♪
1. バーってどんなところ?
「バー」とひとことで言っても、お店ごとに雰囲気やスタイルはさまざまです!
落ち着いた空間でリラックス
店内の照明はほどよく暗く、ゆったりとした音楽が流れる…そんな落ち着いた雰囲気のバーが多いんです。照明やインテリアにこだわった空間で、日常の忙しさを忘れてリラックスできる時間が待っています。
種類豊富なお酒が揃う
バーでは定番のカクテルはもちろん、ワインやウイスキー、クラフトビールなど、さまざまなお酒を楽しむことができます!特にバーテンダーが作るカクテルは、お酒が苦手な方でも飲みやすいものもたくさんあるので、安心して楽しめますよ♪
どんな過ごし方もOK!
一人で静かに過ごしたり、バーテンダーとの会話を楽しんだり、友人や恋人と一緒に賑やかに過ごすこともできます。お店ごとに楽しみ方が変わるのもバーの魅力です!
2. バーの魅力って?
バーには、日常をちょっと特別にしてくれる魅力が詰まっています。
新しいお酒との出会い
バーテンダーに「おすすめの一杯をください」と伝えてみると、まだ出会ったことのないお酒やカクテルを提案してくれることも!「こんなお酒があったんだ!」という驚きや喜びが、バーならではの楽しみ方です。
自分だけの時間を楽しむ
仕事終わりにふらっと立ち寄り、静かに一杯のお酒を楽しむのも大人の過ごし方。静かな音楽を聴きながらグラスを傾ける時間は、心を落ち着かせてくれる最高のリラックスタイムです。
大切な人との特別な時間
バーはデートや記念日にもぴったり!特別なカクテルや上質なお酒、落ち着いた雰囲気が、大切な人との時間をさらに素敵に演出してくれます。二人だけの思い出の場所になること間違いなしです♪
3. バーって敷居が高い?初めての方でも大丈夫!
「バーに行ったことがないから緊張する…」という方でも大丈夫!初めてでも楽しめるポイントをお伝えします♪
迷ったらバーテンダーに相談
「どんなお酒が好きですか?」「甘い系?さっぱり系?」と気軽に相談してみてください。あなたにぴったりの一杯を作ってくれますよ!
お酒が苦手でも安心
バーには、ノンアルコールカクテル(モクテル)やソフトドリンクもあります。お酒が飲めない方でも、おしゃれな雰囲気をしっかり楽しめます♪
スマートに過ごすコツ
バーは静かな時間を楽しむ場所なので、大声で騒がないことや、マナーを大切にすることがポイント。周りの雰囲気に合わせて過ごせば、自然と心地良い時間を楽しめますよ♪
次回予告!
次回は「バーで楽しむおすすめドリンク」をテーマに、バーに行ったらぜひ飲んでほしい定番カクテルやウイスキーをご紹介します!お酒初心者の方から、お酒好きの方まで楽しめる内容ですので、お楽しみに♪
あなたの心に残る「特別な一杯」を見つけるお手伝いができれば嬉しいです!
それでは、次回もどうぞお楽しみに!
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
「一生モノのコミュ力」🗣️✨
夜職の魅力は、収入や華やかさだけではありません。
実は、スナック・ラウンジ・バーで働くと、どんな仕事でも活きる “人間力” が鍛えられます💪✨
「コミュ力」と言うと、話が上手いことだと思われがちですが、夜の現場で求められるのはもっと深い力です。
それは、相手の感情を読み、空気を整え、居心地をつくる力。
これが身につくと、人生がかなり楽になります😊🌙
目次
夜の店では、初対面の人と話す機会が多いです。
最初は緊張します😅
でも慣れてくると、
・相手が話しやすい話題
・触れていいこと/ダメなこと
・会話の温度感
が自然に分かるようになります👀
「話題がない…」ではなく、
相手の“好き・得意・誇り”を引き出す 方向へ会話を運べるようになるんです✨
これは営業、接客、事務、管理職、どんな仕事でも強烈に役立ちます📈
夜職は、会話の主役が必ずしも自分ではありません。
むしろ、お客様が主役の時間。
だからこそ、聞く力が磨かれます。
・話を奪わない
・結論を急がない
・共感はするけど、流されない
・適度に笑いを入れる😂
・相手のテンポに合わせる
この技術は、身につくと本当に強いです🧠✨
人は「理解された」と感じると心が緩みます。
その瞬間を作れる人は、どこでも信頼されます😊
夜の店の気配りは、細かいです。
・グラスが空いてないか🍷
・会話に入れていない人がいないか👀
・席の雰囲気が重くなってないか😮💨
・飲みすぎていないか🚫
・タバコや匂いが苦手そうじゃないか🌿
こういう“観察”が日常になります。
最初は意識しないとできませんが、続けるほど習慣になります。
すると、普段の生活でも
「相手が困る前に動ける人」
になっていきます😎✨
夜職は、ただ会話するだけではなく、場全体の空気を作ります。
・賑やかすぎると疲れる
・静かすぎると盛り上がらない
・誰かが目立ちすぎるとバランスが崩れる
この調整ができる人は、ほんとにプロです🏆
スナックなら“家庭的な安心感”、ラウンジなら“品のある華やかさ”、バーなら“世界観の一貫性”。
こういう空気を守るのが仕事であり、同時に魅力です🌙✨
夜職は、身だしなみや所作を意識する場面が多いです。
派手になるという意味ではなく、清潔感と品を作る力 が育ちます✨
・姿勢を意識する
・言葉づかいを選ぶ
・相手に合わせた距離感を取る
・自分の見せ方を調整する
これができるようになると、普段の人間関係でも得をします😊
夜の店には、いろんな人が来ます。
機嫌がいい日もあれば、疲れている日もある。
だからこそ、感情に巻き込まれない力が必要になります。
・相手の機嫌=自分の価値ではない
・受け止めるけど背負わない
・距離感を守る
この感覚が身につくと、心が安定します🧠✨
※ここはとても大事で、良いお店ほど「スタッフを守るルール」があります🛡️
無理な飲酒やハラスメントを許さない、困ったらすぐ相談できる、など。
安心がある職場ほど、成長も早いです😊
まとめ
夜職の魅力は、
✅ 初対面でも会話を作れる
✅ 聞く力が鍛えられる
✅ 気配りが習慣になる
✅ 場づくりができる
✅ 所作と言葉づかいが整う
✅ メンタルが強くなる
という 一生モノの人間力 が身につくことです🌙✨
「夜の経験」は、昼の人生も強くします😎🍸
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
「大人の居場所」をつくる仕事✨
「夜の仕事」と聞くと、キラキラしたイメージだけが先行したり、逆に偏見で語られたりしがちです
でも、スナック・ラウンジ・バーの本質は、派手さよりも “人の気持ちを整える場所” をつくることにあります
仕事で疲れた人、家に帰っても気持ちが落ち着かない人、誰かと話したい人。
そういう人が「今日はここに寄ろう」と思える場所が、夜の店です。そこには、昼の世界とは違う“やさしい時間”が流れています✨
目次
家でも職場でもない、もう一つの居場所。
スナックやバーは、まさに大人の“第三の居場所”です️
・仕事の愚痴を吐いて笑える
・誰にも言えない不安を、少しだけこぼせる
・今日は頑張った自分を、そっと褒めてもらえる
こういう時間って、意外と人生に必要なんですよね。
「ただ飲む場所」ではなく、気持ちを軽くする場所。
それを支えるのが夜職の魅力です
スナックの良さは、なんといっても距離感。
常連さんが多い店では、初めて来た人も“輪”に入りやすい空気があります☺️
ママやスタッフの役割は、盛り上げ役というより “場の温度を整える人”。
誰かが話しすぎたらバランスを取り、静かな人がいたら自然に話題を振る。
全員が心地よくいられる空気をつくるのは、実は高度なスキルです✨
スナックは「人生の先輩」が集まることも多く、
会話の中に学びやヒントが転がっているのも魅力です
恋愛、仕事、人間関係、お金、家族…リアルな経験談ほど参考になるものはありません。
ラウンジは、スナックより少し“非日常”寄り。
落ち着いた空間、丁寧な所作、きれいなグラス、照明、香り…。
空間全体で「特別な時間」を演出します
ここで磨かれるのは、会話だけではありません。
・言葉遣い️
・姿勢や歩き方♀️
・気配り(タイミング、間、空気読み)
・身だしなみの整え方
こうした“魅せ方”が自然と上達していきます✨
ラウンジの魅力は、ただ明るく盛り上げるより、
相手の心をほどく会話 ができるようになること。
これができる人は、どの世界でも強いです
バーは、店によって世界観がまったく違います。
静かに音楽を聴く店、カクテルが主役の店、スポーツ観戦の店、一人客が多い店♂️…
“空間の個性”がはっきりしているのが魅力です✨
バーテンダーやスタッフは、ただ作業するのではなく、
その店の世界観を守る演出者 でもあります
「今日は強いのじゃなく、やさしい味がいい」
そんな一言から、気分に寄り添う一杯を出せるのがバーのかっこよさです✨
夜職のすごいところは、話術よりも“聞く力”が価値になることです。
人は、正しい答えよりも「分かってもらえた」と感じた時に救われます
・相づち
・目線
・話を遮らない
・否定しない
・でも依存させない距離感
このバランスが取れる人は、本当に強いです✨
お客様から「今日ここに来て良かった」「話して楽になった」と言われる瞬間。
それは、夜職だからこそ味わえる誇りです
夜の店の魅力は、安心があってこそ。
・お酒は無理をしない(無理させない)❌
・ハラスメントを許さない♀️
・危険な飲み方をさせない
・大人(20歳以上)だけの場としてルールを守る
こういう姿勢がある店ほど、長く愛されます
夜職の魅力は、派手さではなく 人を大切にする文化 にあります✨
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
「自己成長」と「経済力」✨
夜職には、昼では得られない成長の機会があります。
それは単なる収入面だけではなく――
“自分という存在価値”を磨く時間でもあるのです。
夜職は努力がそのまま成果に反映される世界。
・接客力
・指名数
・売上構成
・顧客の信頼
これらが数字となり、自分の成長を可視化できます📊✨
月収が10万→50万→100万と上がるにつれて、
「お金を稼ぐ」だけではなく、
「自分の人生を自分で選べる力」がつく。
その自由こそが、夜職の魅力です💎
夜職では、会話一つで信頼関係を築く必要があります。
信頼を得るには、相手を否定しないこと。
そして、自分を作り過ぎないこと。
💬「この人に話すと楽になる」
💬「この子には本音を言える」
そう思ってもらえることが、指名・リピートの第一歩。
つまり夜職は、「人を癒す力」を鍛える仕事なんです🌿✨
夜職で培うスキルは、
営業・接客・経営・心理分野など、どの業界でも通用します🔥
✔ 話を聞く力(ヒアリングスキル)
✔ 相手に合わせた提案力
✔ 継続的な関係構築力
夜職で鍛えられるのは「総合的人間力」。
実は“最強のビジネススキル訓練場”なのです💼✨
自分で稼ぐ力がつくと、
「自分の価値を自分で決められる」ようになります。
💄美しくあること
💬話せること
💰稼げること
🕊️信頼されること
これらを自分の努力で掴んでいく――
夜職は、“自分の人生をデザインする仕事”です🌈
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
夜の街。
ネオンが灯り、音楽と笑い声が混ざり合う中で、
今日も誰かが“自分という光”を放っています💄
夜職――それは、ただお酒を出す仕事でも、
ただ接客をする場所でもありません。
それは、“人間を学ぶ場所”です。
昼職では感じられないスピードで、
相手の感情を読む力・会話の反応力・表情の変化を掴む力が磨かれていきます🌟
💬お客様が何を求めて来ているのか?
💬今日のテンションはどうか?
💬一杯目の飲み方でどんな性格かわかるか?
夜職は、心理学と人間観察の現場です👀✨
数分の会話で「心の距離を詰める」ことが求められる。
だからこそ、夜職の人たちは本能的に“空気を読む達人”になります。
「夜は見た目が全て」と言われがちですが、
それは誤解でもあり、同時に真実でもあります。
💅髪・メイク・服装・立ち振る舞い――
それらを毎日磨き続けることで、
自然と“自信”が身に付く✨
その努力は、どんな職業よりも地道。
夜職で輝く人ほど、裏では想像を超える自己管理をしています。
🌸スキンケア
🌸食生活
🌸睡眠リズム
🌸メンタルの整え方
“見せる仕事”は、同時に“内面を鍛える仕事”でもあるのです💫
夜職で最も大切なのは、
「自分を売ること」ではなく「相手を理解すること」✨
本気で人に向き合うと、
その誠実さは自然と返ってくる。
夜の世界で結果を出す人は、
必ずと言っていいほど“人が好き”です💖
だからこそ、夜職は“もう一つの学校”。
学ぶことは多く、卒業しても役立つスキルが詰まっています🌙
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
~“リスニング&リーディングバー”~
“聴く”“読む”“語る”ための静かな設計——それが、リスニング&リーディングバーです。
今回は、初めての方にも伝わる席の選び方・音の楽しみ方・本棚の歩き方・おすすめの一杯まで、まるっとご紹介。混ぜない文化が、夜をゆっくりと豊かにしてくれます。
目次
音:アナログ盤/真空管/木製ホーン。音量は会話を邪魔しない“深さ優先”。
灯り:3000K前後の暖色。グラスの縁と紙の地が綺麗に見える明るさ。
紙:詩集・写真集・建築・食・旅。分野は雑多、でも“触りたくなる”装丁だけを選書
混ぜないバー=情報の洪水からの避難所。耳と目の感度を、ゆっくり取り戻しましょう。
スピーカー正三角の“甘い席”:音像がピタッと定まる特等席。
カウンター端:バーテンダーと静かな会話、本のおすすめも。
壁際ソファ:読書に没頭。ページをめくる音がBGM。
スタンディング棚前:10分だけの寄り道に。1杯で立ち去る潔さも美しい。
選曲リクエストOK(在庫の範囲で)。曲名・アーティスト・盤の年代がわかるとスムーズ。
1曲は約3〜6分。曲間の無音も味わいです。
シャッターは1枚だけ。音を吸う空間に、氷の音を残しましょう
本は自由にどうぞ。コースターをしおり代わりに使えます。
背表紙の言葉で選ぶ遊び:「余白」「旅」「透明」「うた」。ピンと来た本は、今の気分に正直。
持ち込みのZINE歓迎。置いていってくれたらスタンプを押します✒️
シングルモルト・“本の相性”セレクション
詩集には蜂蜜と花のニュアンス、建築本にはミネラルと直線を感じるアイラの一杯。
日本酒・“紙の手触り”セレクション
和紙のように柔らかな口当たりの生酛、活版印刷の凹凸みたいな酸のきいた山廃。
ナチュールワイン・“余白”セレクション
少し還元から始まり、空気で開く。20分後の別人を楽しんで。
ノンアル
深煎りハンドドリップ(12oz)/ほうじ茶の低温出し/トニックにグレープフルーツピールだけを一滴(砂糖ゼロ)。
ビル・エヴァンス × 写真集 × バーボン少量:ピアノの余韻とバニラウッドが溶ける。
ニーナ・シモン × 詩集 × シェリー樽モルト:低音とドライフルーツの会話。
環境音楽 × 旅エッセイ × 微発泡白:ページをめくるたびに泡が言葉を押す。
ローファイ × ZINE × ナイトロコーヒー:紙のザラつきと泡のきめで、時間がほどける。
混ぜないバー最大の贅沢は時間の味。
注いで3分:トップノート(柑橘・花・スモーク)。
10分:中域(穀物・蜜・樽)。
20分:低域(スパイス・土・カカオ)。
同じグラスでもページの位置で味が移ろう——それを感じられた夜は、とてもいい夜。
酵母バターのパン:淡い塩味がウイスキーの甘香を押し上げる。
燻製ナッツ:ワインの還元をほどく。
昆布・鰹のお出汁(少量):日本酒の旨味レイヤーが“見える化”。
ビターチョコ:ラム/ポートの余韻を伸ばす。
アルバム完全再生の夜:A面からB面まで通しで。曲間の針の音を楽しむ会。
選書&注ぎ手ゲスト:書店員×バーテンダーで“紙と液体”のクロストーク。
持ち込み盤の会:1人1曲ずつ。曲にまつわる短い物語を添えて。
朝の読書会(ノンアル):深煎り一杯と静かな30分。
合言葉「ページと針」で席チャージ半額
一人で浮きませんか? → おひとり様が基本形の店です。
注文が不安 → 風景語でOK。「森」「港」「図書室」など️
写真は? → 1枚だけ、シャッター音にご配慮を
長居していい? → 書き物・読書歓迎。満席時はお声がけします。
混ぜないバーは、派手さの代わりに深さをくれる場所。
レコード針が落ちる音、ページをめくるサラリ、氷が鳴るカラン。そこにあなたの一杯が静かに重なれば、世界は少しだけ優しく見えます。
次の曲、次のページ、次の一滴。今夜もお待ちしています
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
~“素の一杯”~
カクテルは出しません。シェイカーも振りません。
それでも、いや、それだからこそ——グラスの中に宇宙が広がる。当店は、ウイスキーやラム、テキーラ、ジン、日本酒、ワインなどをストレート/ロック/加水/温度違いで楽しむ、「素材直球」のバーです。混ぜないことは、香り・温度・時間の三要素と真っ直ぐ向き合うこと。この記事では、初めての方でも緊張せずに楽しめる注文のコツ・飲み方・ペアリングをまるっとご紹介します。今夜の一杯に、少しの冒険を
目次
味の起点がシンプル:加糖・酸味・炭酸の“足し算”がないから、産地や樽、蒸留の違いがダイレクトにわかる。
会話が深まる:原材料・熟成年数・香りの変化を、バーテンダーとゆっくり対話できる。
体調に合わせやすい:少量のテイスティングから始めてOK。グラス半量・1/3量、遠慮なくどうぞ。
翌日に優しい(個人差はあります):砂糖・酸の摂取が少なく、ペースを自分でコントロールしやすい。
当店の合言葉は「混ぜない自由」。足し算の代わりに、温度と時間の引き算で味を整えます️❄️
「やさしい・甘やかで」→ バーボンのバニラ系、ラムのトロピカル系。
「香り高くて軽やか」→ ジンのボタニカル、若いシェリー樽ウイスキーのドライフルーツ。
「しみる渋みが欲しい」→ ライウイスキーのスパイス、ネッビオーロ系ワインのタンニン。
「土と風を感じたい」→ アガベ100%のテキーラ/メスカルの燻香と土気。
「低アルで長く」→ 日本酒の冷やを小ぶりのぐい呑みで、または酸強めの白を小量ずつ
銘柄がわからなくても大丈夫。風景の言葉(海・森・焚火・果樹園)で十分に伝わります
冷やす:香りの輪郭がシャープに。高アル原酒は冷やすと刺さりが和らぐ。
室温:香りが立体化。果実味や穀物香が豊かに。
温める:日本酒や一部のラムは旨味と甘香が前へ。55℃の燗で世界が変わることも。
加水1〜2滴で香りがパッと開く瞬間がある。
ウイスキー原酒は加水比1:1まで別人格。合う・合わないは実験あるのみ
ミネラルウォーターは軟水/硬水を選べます。味の“ノリ”が違う
スワリング(軽く回す)→ 香りが立ち上がる。
時間経過で表情が激変。5分・10分・20分、メモしてみると楽しい⌛
チューリップ型:香りを集め、アルコール感を逃がす。多くの蒸留酒に万能。
ロックグラス:氷の表面積と口径の広さで、香りを“寝かせる”。
薄張り:唇の感触が軽く、果実味・旨味がダイレクト。
氷:透明・溶けにくい丸氷/角氷をご用意。氷の割れる音もご馳走です
ナッツの塩味 × シェリー樽ウイスキーの干し葡萄感
ドライ無花果/チョコ70% × ラムのモラセス&バナナ
燻製チーズ × スモーキーなモルト(ヨード/潮風)
出汁ナッツ・昆布 × 日本酒のアミノ酸の旨味
柑橘ピール × ジンのシトラスボタニカル
→ 一口の相互作用で、グラスの印象がくるっと変わります
モルト3点旅:バーボン樽/シェリー樽/ピーテッド(各15ml)
ラムの産地巡り:マルティニークAOC/ジャマイカ/グアテマラ(各15ml)
日本酒温度違い:冷や(12℃)/ぬる燗(40℃)/上燗(45℃)(各60ml)
ジンの香草図鑑:柑橘系/スパイス系/グリーン系(各15ml)
少量ずつだから酔いすぎず、でも違いはくっきり。旅のしおりもお渡しします
シングルオリジン炭酸水:産地で味が違う?を体験。
発酵ティー(烏龍・紅茶):温度で香りが上下する面白さ。
ナイトロコーヒー:窒素のクリーミーな泡で、麦芽のような余韻。
季節の搾りジュース微発泡:柑橘や林檎を軽い泡で。砂糖控えめ
→ アルコールと同じグラスで提供。場を共に楽しめます。
強いお酒が苦手です → 加水・少量・低ABVの選択で調整します。
値段が心配 → 量×価格を明記。15ml/30ml/60mlで選べます。
難しそう → 風景でOK。「森っぽい」「果樹園」「焚火」。その一言がヒント
食事は? → 軽いつまみ中心。持ち込み可の曜日もあります(SNSで告知)。
水の研究会:軟水・硬水・炭酸の違いで香りがどう変わる?
温度と日本酒:同じ銘柄を温度だけで比較する“燗の学校”
ミニテイスティング:5種×10mlの“香りの散歩道”。
合言葉「混ぜない自由」でテイスティング1種サービス
足し算をやめたら、素材の物語がまっすぐ届いた。
樽の年輪、畑の土、蒸留所の朝霧、造り手の手。グラスの中、音もなく広がる世界に、あなたの好きが見つかりますように。
今夜、一滴の冒険を。お席、あいています✨
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
~鉄則~
水商売(バー/クラブ/ラウンジ/ホスト・キャバ等)は、“夜の接客 × 事業運営”の両輪です。
売上だけを追っても、無理売り・トラブル・離客で続かない。雰囲気だけでも、数字は守れない。
ここでは、今日から現場で機能する鉄則を12章に整理しました。法令名や基準は地域で異なるため、最終判断は必ず地元の所轄と店舗規程で確認してください(以下は実務の原則)。
目次
年齢確認は絶対:身分証の原本確認。未成年・泥酔者への酒提供は不可。
営業時間・広告・同伴ルール:所轄の許可条件に適合(表示義務・看板表記・照度など)。
記録を残す:入退店・トラブル・支払いは台帳化。“言える化”=守りの武器。
源氏名・連絡先分離:私物番号・自宅・通勤経路を開示しない。送迎は店手配で。
帰路のリスク管理:終電逃し・待ち伏せ対策、ドアtoドアで共有。
ハラスメントの即時切替:合図→席替え→会計→退店のフローを全員が共通認識。
観察→共感→話題:手元(時計・名刺・グラス残量)→共感一言→開いた質問。
名前を“2回”呼ぶ:着席直後・乾杯直後に自然に。記憶は接点で定着。
ミラーリングは控えめに:声量・テンポ・姿勢を“1段階だけ”合わせる。
基本の順序:セット → 延長 → 指名(or場内) → ボトル/シャンパン → 同伴/イベント。
提案のタイミング:残り30分で延長確認、2杯目でボトル提案、記念日でハレ演出。
言い回し例
延長:「せっかくなので、あと30分だけお話ししてもいいですか?」
ボトル:「次も同じお味がお好きなら、こちらの方がお得で長く楽しめますよ」
当日:お礼+席での話題を1行で復習(既読スルー前提の短文)。
48時間内:写真・イベント告知ではなく、その人だけの一言。
72時間内:次回の“理由”を用意(新作ボトル、音楽、フード、他愛ない口実)。
CRM:来店履歴・好み・NG・記念日・同伴可否を個人カルテに。
合図の統一:延長可否/会計察知/飲ませNG/席替え要請のハンドサイン。
ヘルプの心得:主役を食わない、会話の“橋”だけ架ける。
衝突回避:担当・場内・同伴の優先順位ルールを冒頭で共有。
マイドリンクの設計:交互にノンアル、水分・電解質を必ず挟む。
睡眠と食:閉店後すぐ糖質に走らずタンパク+温かい汁物。
声帯と肌:加湿・のどケア・帰宅後のクレンジング徹底。見た目=資本。
現金管理:レジ締めと個別チップ等の区分を厳格に。
貯蓄の自動化:入金日の先取り天引き(30%目標)。
税申告:領収書・交通費・衣装・通信費の記録。**“白黒”より“継続”**が信用に直結。
NGの伝え方:「それはお店のルールでできないんです。代わりに…」
連絡頻度の線引き:返信は営業時間内、夜間の連絡は翌日。
個別会い控えの型:「安全のため、プライベートでは会わないんです」
型を決める:出勤表・感謝・新入荷・衣装・趣味の5カテゴリで回す。
位置情報・生活動線NG:自宅最寄り・習慣の特定につながる投稿は避ける。
ネガは“店内で解決”:SNSでの愚痴・暴露は長期ダメージ。
支払い不履行:即、責任者→レシート・オーダー台帳→警備/所轄連携。
泥酔・嘔吐:安全確保→清掃・消毒の手順→次回出禁判断は複数で。
ストーカー化兆候:単独対応せず、店長・所轄・ビル管理と共有。記録を残す。
客単価/延長率/ボトル比率/指名本数/リピート率。
新規→再来(72時間内)、クレーム件数、ドリンク原価率。
週1で3つだけ改善:台詞、提案タイミング、SNS導線など“小さく回す”。
初対面:「はじめまして、◯◯です。お仕事の前後どちらですか?」
延長提案:「あと少しお話ししたいです。30分だけ延長しませんか?」
ボトル提案:「この前お好きって言ってた◯◯、ボトルだとコスパ良くて長く楽しめます」
NG対応:「ごめんなさい、ここはお店のルールでできないんです。代わりに…」
A3一枚の“店内ルール”:年齢確認・ハラスメント・延長確認・退店フローを図で掲示。
72時間フォロー運用:お礼→個別一言→次回理由。テンプレをチームで共有。
KPIの週次レビュー:客単価・延長率・リピート率の一枚ダッシュボードで改善を継続。
水商売の鉄則は、安全・信用・数字の三拍子です。
境界線を守り、心地よい時間を作り、約束した価値を毎回届ける。
それができるお店・人から、常連は自然と積み上がります。今日の一席を、丁寧に。
![]()
皆さんこんにちは!
BEER BAL LIONの更新担当、中西です!
LIONのTPICK
~バーの未来~
“お酒を出す場所”から“時間をデザインする場所”へ。これからのバーは、多様な飲み方・安全性・環境配慮を軸にアップデートが進みます。実務に落とせる形で、方向性と設計ポイントをまとめました。
目次
ロー/ノンアルの常設(平日・連日でも楽しめる選択肢)
体験価値の重視(音・光・香り・物語)
キャッシュレス/予約・会員制の普及で常連の可視化
安全・コンプラ期待の上昇(年齢確認、過度提供防止、ハラスメント対策)
ハイブリッド運営
昼=コーヒー&軽食/夕方=アペロ/夜=バー。席稼働を一日で積み上げる。
三層メニュー
クラシック(誰でも)/シグネチャ(店らしさ)/ノンアル(同等クオリティ)。
オーディオ&ライティング
耳と目の“解像度”が滞在満足を決める。音圧は会話が崩れないレンジで統一。
サステナブル
シトラス皮の再利用、ドラフト・プレバッチで廃棄とブレ低減。
セーフティ・ホスピタリティ
年齢確認・提供量管理・帰宅手段の提示・アンチハラスメントの掲示。
着席制・時間枠でRevPASH(席時間あたり売上)を最適化。
アナログ~ハイレゾまで“選曲=体験”。低アル・ノンアルを半数ラインナップ。
完全予約・コース設計(季節6杯+小皿)で粗利と体験の両立。
物語設計:産地・技法・器のストーリーを一続きに。
手頃な価格×早い提供。ドラフト/プレバッチで回転を上げる。
コミュニティ運営(読書会、ボードゲーム、昼はワークテーブル)。
価格三段階:入門/主力/限定。原価率を帯で管理(例:25%/22%/28%)。
ノンアルは“引き算”でなく“別ジャンル”:ビターノンアル、スパイス、発酵、ティーベース。
ドラフト&プレバッチ:均一品質+提供10秒台。繁忙時に強い。
アレルゲン/糖分表記で安心を見える化。
カウンター主役:手元が“舞台”。製氷・グラス・ガーニッシュを最短動線に。
光:顔はやわらかく、グラスは立つ(2700–3000K+スポット)。
音:会話を邪魔しない音圧に固定、吸音で反響を抑える。
におい:香水・調理臭の衝突を避ける換気計画。
年齢確認、提供量の見える化(杯数ログ)
過度な勧誘・誤認を生む表示の禁止(料金は多重掲示)
迷惑行為の通報手順と退店ルールを掲示
スタッフ教育:酔客の断り方台本/ハラスメント対応
ゼロウェイスト設計:皮→シロップ/ピールパウダー、果肉→スカッシュ、端材→ガーニッシュ乾燥。
ローカル調達:季節果実・クラフト・茶葉。
省エネ:氷管理、インバータ冷機、LED・タイマー。
RevPASH(席×時間):客単価×回転率で設計。
ミックス:ノンアル比率20–30%、フード比率20–40%。
コスト:飲料原価22–28%/フード30–35%、人件費25–30%、家賃10%前後。
再来率・会員比率:月次でトラッキング。
0–30日:現状KPIと客層分析/ノンアル&ローABVの試作会
31–60日:ドラフト・プレバッチ導入、料金掲示と安全ポスター整備
61–90日:音・光の微調整→ソフトリニューアル/会員制を試験運用
「飲まない夜も、満ちていく。」
「音と一杯、60分の旅。」
「低アルでも“手抜きゼロ”。」
これからのバーは、体験設計×安全運用×サステナブルで“また来たくなる理由”を増やすこと。
メニュー三層化・ドラフト/プレバッチ・音と光の最適化・可視化された安全——この4点を押さえれば、収益と評判は同時に伸びます。最初の一歩は、ノンアルの常設強化と料金表示の再設計から。
![]()